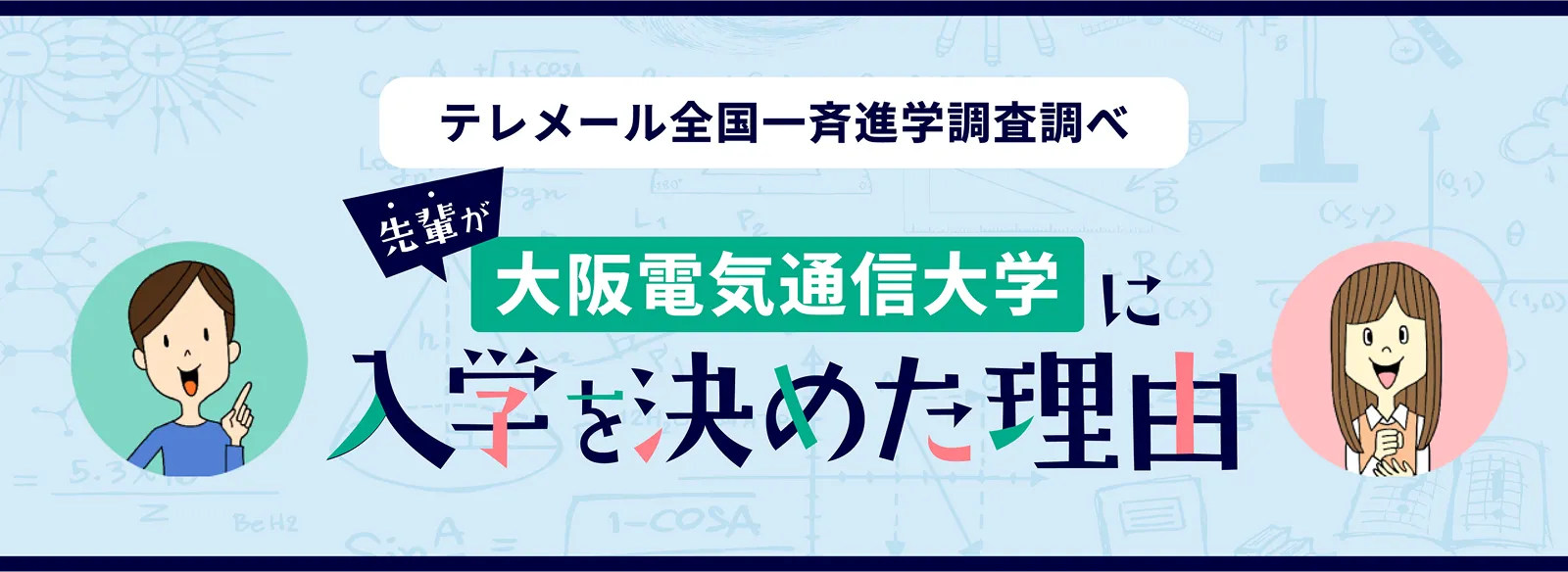現在の仕事内容
研修と一級建築士の勉強。
歴史ある建築事務所で基礎を固める日々。
わたしは今、90年以上の歴史がある東畑建築事務所で設計者として働いています。一般的には意匠設計と呼ばれる、建築の計画やデザインなどを決めることが仕事です。今は研修中ですが、大学の授業で学んだ内容が実際の業務にも出てきており、実社会に役立つ学びを得られていたのだと改めて感じました。
東畑建築事務所は研修がとても充実しています。ようやく研修の最終段階を迎えていますが、現在は基本的な寸法感覚を身につけるために事務所内のトイレや階段を計測して図面を書き起こすなど、建築の基礎を学ぶ研修が中心。また、一級建築士の資格取得も目指しているので、研修と資格取得に向けた勉強という建築一色の毎日です。

入職したきっかけ
憧れの設計事務所で仕事をするために
大学院で建築に対する考え方を深める。
大学2年次に参加した関西最大級の建築イベント「生きた建築ミュージアムフェスティバル大阪」で東畑建築事務所を知り、興味を持ちました。大阪をはじめとして多種多様なビルディングタイプを手掛ける設計事務所で「いろんな経験ができそう!」という興味と、出身地である大阪で設計の仕事がしたいという気持ちがあったので東畑建築事務所を目指しました。

大学院では、大学で取り組んだモルタル系3Dプリントによるベンチのデザインと制作の実績をもとに、わたしの考える「iF Architecture」※という建築の概念のもと、人と社会と建築の関係に「気づき」をもたらす建築の提案を研究テーマに取り組みました。
- 日常の何気ない気づきを大切にすること。「iF Architecture」とは気づきを与える建築である。日常にさりげなく存在しつつも、気づきを与えるためには、人、環境、歴史とさまざまなものに共鳴するような建築の決め方をする必要がある。最先端テクノロジーを導入しつつ、地域のコンテクストや、歴史、人のふるまい、土木的要素などと橋渡しをするきっかけとなる建築の提案のこと。

仕事のやりがい
いつかは公共的施設の設計を手がけ、
より良い社会づくりに貢献したい。
設計者にとってのやりがいは、設計がカタチになること。まだ研修中ですが、先輩方の仕事を身近に感じることで、毎日刺激を受けているのでコツコツと経験を積み重ねて、一人前の設計者になれるように頑張っています。
わたしは将来、公共的施設の設計に携わりたいと考えています。人、地域性、時間軸などいくつものベクトルが複雑に絡み合ってできているのが建築。その建築の将来性、存在する意義、社会に与える影響など、設計者が多角的な視点で捉えて設計することが重要で、そうして設計された建築はより良い社会づくりに貢献します。貢献といってもさまざまな形がありますが、まずその建築がしっかり利用されること。そして利用した人たちが笑顔になること。さらにそのパワーが周辺にまで波及していくことで、社会的に意義があるものになると考えています。そんな「愛される建築」を目指して頑張っていきたいと思っています。

大学に入学したきっかけ
これからの時代に求められる設計士になるために、最先端のツールを学べる大学へ。
子どもの頃から絵を描いたり、粘土などで立体を作ったりすることが好きでした。特に遠近法で立体を描くことに興味があり、頭の中の立体を何らかの手法でアウトプットすることが好きだったんだと今振り返ると思います。一時期は伝統工芸士になろうという思いもありましたが、色々と考える中で設計者の道に進むことに。そのきっかけの一つが高校で学んだマーケティングの授業でのこと。自分が考えた店舗の設計をするという課題について考えている時、設計を生業としている父からアドバイスを受け、普段何気なく使っていた家や学校などの建物は、様々な人々が関わり、工夫し、思考された「叡智の結晶」であるいうことに気づきました。例えば、屋外に接する建具には雨水が溜まらないように水切りがついていたり、直射日光を考慮した庇の形状、窓の位置など、普段のあたりまえに気づいたとき、「建築という行為」を認識し、とても魅力的だと感じたので建築の道に進みました。進路を決める際、専門学校や短期大学という選択肢もありましたが、親のアドバイスもあって大学の建築学科を目指すことにしました。
大阪電気通信大学は、BIMなどのデジタル教育に力を入れているという教育方針があり、これからの時代に必須な力がここで身につけられると思いました。建築に携わる者として、テクノロジーが急速に進化する中で建築のあり方について考えなければなりません。大学では建築の基礎や実践的な授業を通してさまざまな学びを得ると同時に、最先端のツールを修得し経験豊富な先生たちから教わったことで、未来の建築業界で活躍するための素養を身につけられたと思います。

印象的な大学での学び
井の中の蛙だと気付かされた経験から、
設計に取り組む姿勢が変わり、学内コンペで最優秀に輝く。
設計のプロセスを学ぶ実習が一番楽しく印象に残っていますが、自分の中でのターニングポイントとなるのが、2年次前期での出来事。設計実習課題で建築新人戦というコンペに挑戦したことです。設計に関しては学内でも評価されていたので自信はありましたが、全国の優秀な学生たちのレベルの高さを肌で感じて、正直、悔しかったです。この経験を活かそうと建築に対する考え方や姿勢を変えて、これまで以上に作品作りに没頭。大学の同期でありライバルでもある仲間と夢中になって外部コンペに参加し続けました。すぐに結果が出なくても諦めずに何度も挑戦できたのは、一緒に走ってくれた同期の存在が大きかったです。いろいろと挑戦したことで能力が身につき、1年後の新人戦で入賞という結果につながりました。
学生時代の集大成となるのが、2021年に行われた大学の寝屋川キャンパスの「OECU広場West」のコンペで最優秀賞を受賞したことです。学園創立80周年を記念して、広場のデザインを学生から公募したコンペでしたが、わたしたちのチームの案をもとにした広場が設計され、2023年8月に完成。学祭の時にその広場で子どもが遊んだり寝転がったりと楽しそうにしている姿を見て、自分が設計したものがカタチになる喜びを実感できました。

受験生へのメッセージ
最先端のツールに触れられ、経験豊富な先生が支えてくれる。
ここには、建築に興味のある人が成長できる環境がある。
大阪電気通信大学の魅力は、やはり最先端のデジタルツールに力を入れていることだと思います。実務でも作業の効率化や、多角的に考える上で、これらの技術が大いに活躍します。学生のうちから最先端のツールに触れることは貴重な体験ですが、ツールばかり使えても建築ができるとは限りません。泥臭く手書きをすること、本を読み漁ること、人とのコミュニケーションを取ることなど、アナログ的な要素も大切だと感じます。その点で、大阪電気通信大学はデジタルが得意な先生、アナログ的ことが得意な先生、実務に詳しい先生など、各専門分野に精通した先生がいらっしゃいます。先生方のサポートも手厚く、建築に興味がある人が成長できる環境が整っている大学なので、設計や建築に好きな人は、ぜひここで学んで夢を叶えてほしいです。