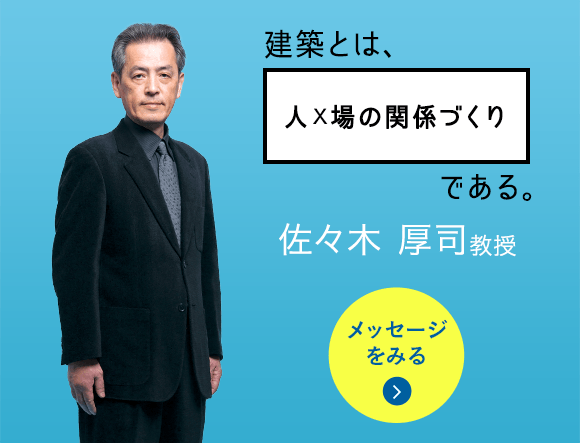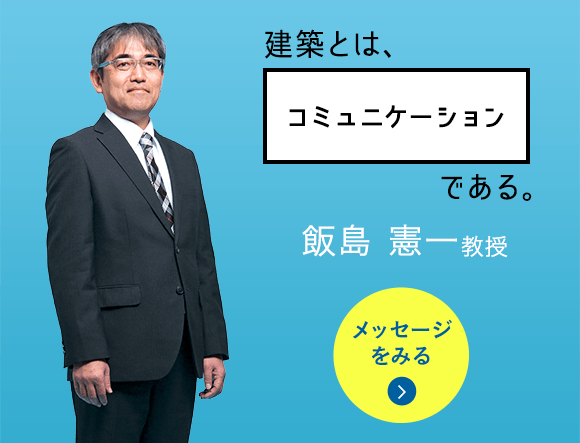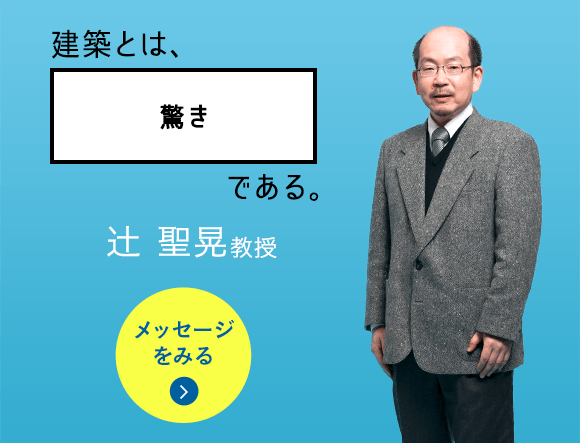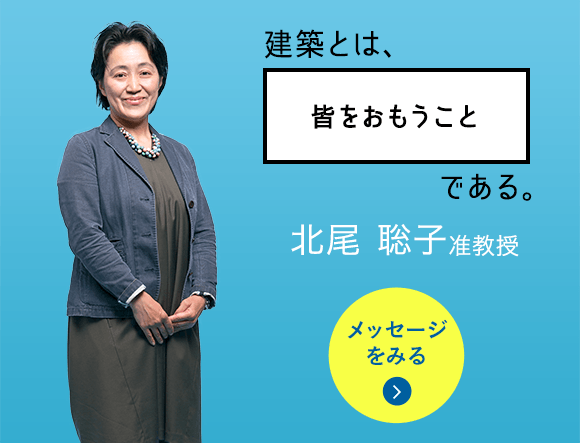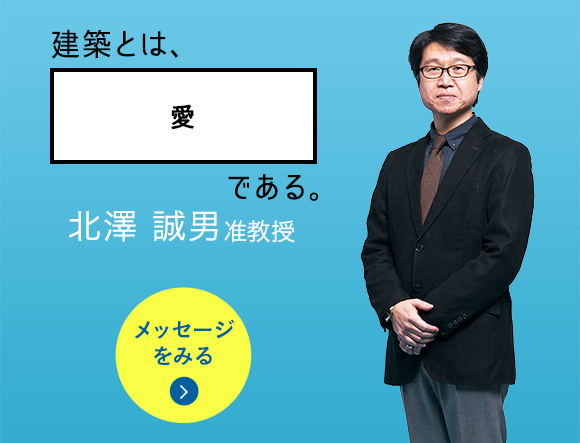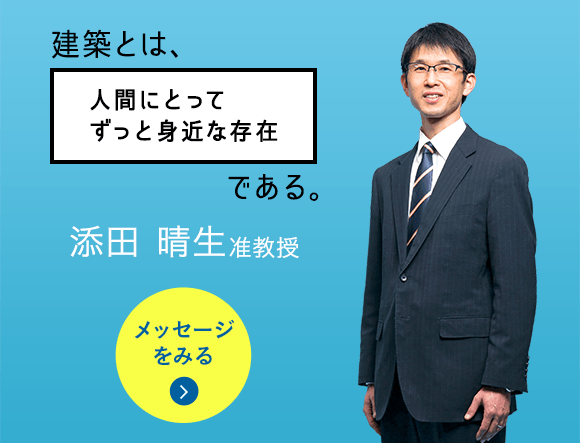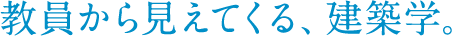
建築とは、いったい何でしょうか?
建築学科の教員の言葉から、「建築とは何か」を探ると同時に、
教員自らの建築に対する思考や想い、さらには人間的魅力まで迫ります。
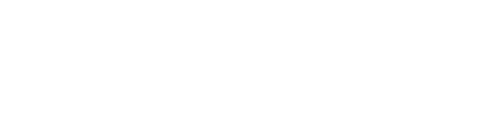
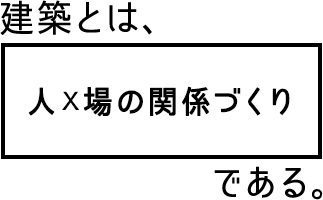
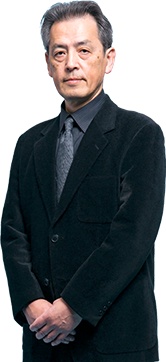
最先端の空間づくりは、
座学だけで学べるものではない。
私の研究は、建築・都市計画、まちづくり計画・設計、都市環境デザインなど、建築から都市に至る参加協働の計画・設計がテーマです。京都・大阪(河内)をネットワークし、「実際の街」再生に向けた参加協働のデザインなど、建築からのさらなるデザインマネジメントに取り組んでいます。着手する段階から地域の人たちを含むさまざまな立場の関係者とコミュニケーションを密にできてはじめて、「空間をいかし」「まちに根づく」ことが可能になります。
研究室では、京阪神の多くの地域で、常に地域、社会と関わりながら建築・まちづくりに取り組んでもらいます。地域の方の話を聴く、地域の行事に参加する、地域の方と一緒にまちづくりを考える、「まちなかインターン」ともいうべきこうした経験は、机上の学習とは全くレベルの異なるものになるでしょう。最先端の空間づくりは、座学だけで学べるものではないのです。
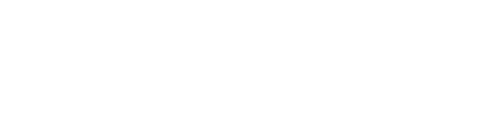
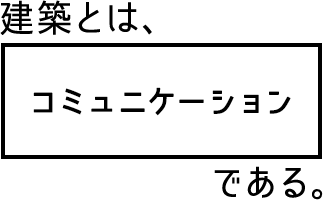

いい建物がつくられるには、
それぞれのプロが能力を発揮する必要がある。
どんな優秀な匠でも建物をひとりで建てることはできません。設計と施工には多くのプロが関わります。いい建物がつくられるにはそれぞれのプロがその能力を遺憾無く発揮する必要がありますが、その基盤となるのがコミュニケーションです。また、建築は「単品受注生産品」であるため、設計者や施工者は常に建築主との合意形成が求められ、ここでもコミュニケーションが重要となってきます。
私の研究は、今建築業界で話題になっているBIM(Building Information Modeling)における設計と生産についてです。BIMは建物データベースとも呼ばれており、プロとプロのコミュニケーション、クライアントとプロのコミュニケーションの基盤になると期待されています。ICTは今後も発展を続け、ますます世の中で重要な位置を占めることになると思います。そしてこの流れは誰も止めることができません。しかし、主体は人間です。よって、ICTを使いこなせる建築技術者がこれから求められているのです。
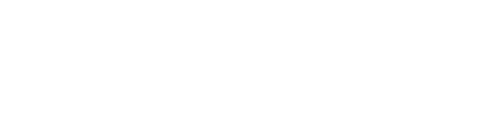
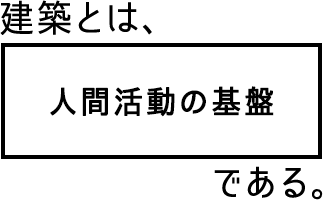

建築は、人間が生きていく基盤。
社会のニーズを感じとることが大切。
建築は、人間が生きていく上で、個を守り、安らかで快適な環境を創り出すもの。人間の活動の幅広い領域でハード面・ソフト面ともに基盤となっています。私の研究は、最適な建築生産技術の研究です。日本は超高齢社会の到来により将来労働力の減少が予想されており、「生産性の向上」が不可欠です。
しかし、最適解は時代・環境・建物特性やその他要因によって異なってきます。これからの建築のプロは、社会が求めているものを感じ取り、社会に貢献していかなければなりません。そのためにも、建築だけでなく、社会への興味も深め、学びの視野を広げておくことが大切です。ひいては、それが建築のプロになった時に自らの「オリジナリティ」へとなっていきます。
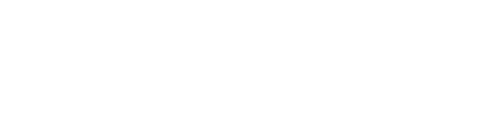
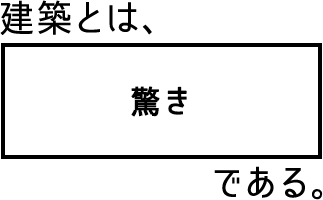

世の中の人々を「アッ」と驚かせる
建築技術者を育てていきたい。
今後日本は人口の減少に転じ、「ゼロから創造」だけではなく、「今あるものをどう活かすか」という観点が求められます。既存の建物を、できるだけ少ない資源で安全・快適な建物に変える技術(リノベーション技術)は、これからの技術者により一層必要とされます。私の専門は建築構造分野で、免震や制振技術を組み合わせて、より安全・安心な建物の実現をめざす「ハイブリッド免制振構造」です。
建築には、さまざまな役割がありますが、そのひとつが、人々に驚きを与え、歴史への敬意と感動を呼び起こすこと。人々に驚きを与える建築を設計し、それを実現できる設計者や施工技術者を育成することが、私の目標です。
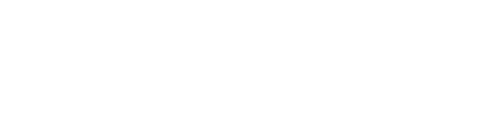
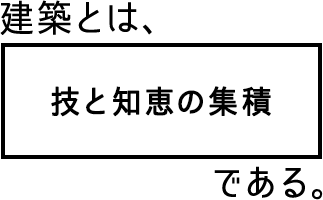

学ぶ対象は、
単なる知識でも技術でもない。
だから、建築学は面白い。
私の専門は建築史であり、歴史に創造力を学ぶ研究です。これから建築のプロをめざす人に必要なのは、瞬発力と持続力、偶然を誘発する直観力、失意を糧にする反発力、諦観する余裕、協調性とコミュニケーション(伝達)力、冷静な判断力、自己責任能力と挙げればきりがありません。
建築とは、常にプラクティカル(実践的)なものです。つまり、人生に似ていて、思い通りになるはずがないということ。それを現実として積極的に受け入れ、それが実は幸運であったことに気づくことで、次につながる。そして、最終はすべて自分の責任だということです。建築は、意外と面白いもの。なぜなら、学ぶ対象は単なる知識でも技術でもなく、多様な技と知恵の集積だからです。
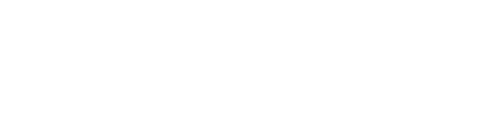
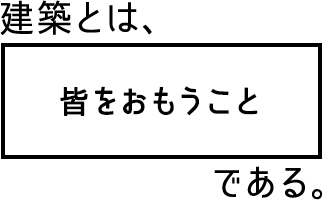

建築は影響力が大きいからこそ、
皆の思いをまとめて、かたちにする。
個人所有の建築物であれば、その建物周辺の方々への影響があります。公共建築物であればなおさらのこと。また建物内部においても、空間の色味ひとつでさえ、人の動きや気持ちに変化をもたらします。このように建築物は影響を与える範囲が大きく、その影響は永らく続くことになります。一度建設した建物は簡単に取り壊すことはできないものです。そんな影響力の大きいものをつくる建築という行為は、責任が重大。ぜひとも、皆をおもいやり、皆の思いをまとめて、かたちにしていくものであると認識しながら建築とつきあってほしいと思います。
大学は、高校までの授業とは少し違っていて、自ら問題を模索・設定し、答えのない問題に果敢に取り組む勇気、そして判断が必要になってきます。勉強する分野に好き嫌いを言わず、好きな内容はとことん好きになって、嫌いな内容も嫌いながらも止めずに継続してください。継続は力になります。
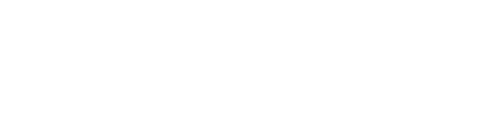
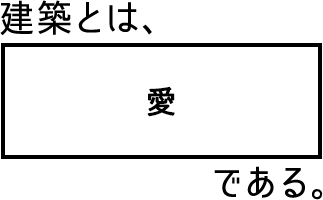

建築で迷う時には
人を想像すれば
すぐに答えが見える。
学生時代から、ファストフード店が世界のどこでも同じ設えであることに違和感を覚えていました。建築家は発注者の要望に単に応えるだけでなく、総合的な視点やマインドを持ち、さらに発注者が間違った考えを持っている場合は勇気を持って「No」と言える建築倫理観が必要です。建築の仕事に携わるなかで、「経済活動・名声・技術」といった目先のことよりも、多くの職人さんに助けられたり、発注者と同じ夢を共有できたり、もっと大切なことに出会えました。
建築とは、関係するすべての「愛情」のもとに存在するのではないかと思っています。空間を創造することは人間生活そのものに関わることであり、建築で迷う時には空間にいる人を想像すればすぐに答えが見えるはずです。だからこそ、「まわりを思いやれること」と「次世代をイメージできること」を大切に学び、建築のスペシャリストへと成長してほしいと思います。
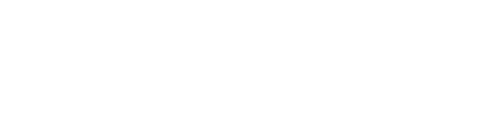
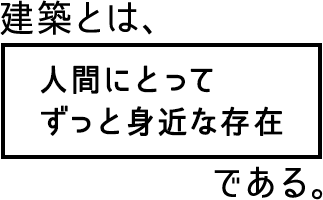

人や安全、環境のことを
真剣に考え、
さまざまな分野に配慮できるスキルが大切。
生活で、職場で、私たちが何かをするとき、建物の中にいます。このように、建築は人間にとって最も身近な技術であり、ずっと身近な存在であるといえます。だからこそ、人間にとって居心地の良い空間や安全な空間が求められるのでしょう。私の研究は住宅の省エネルギー化についてですが、建物は人間だけでなく、常に周りの環境に対しても影響を及ぼすため、環境への配慮も重要です。だからこそ、建築のプロをめざすには、人や安全、環境のことを真剣に考え、さまざまな分野に配慮できるスキルを養ってほしいと思います。
また、コンピューターを用いて、設計をしたり、シミュレーションをしたり、効果的に利用するスキルを身につけてください。コンピューターの能力は計り知れないものがあり、情報技術の恩恵により、建築分野も飛躍的に成長していくものと思います。