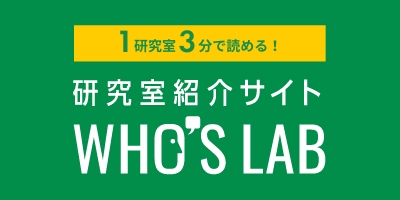設置の装置群 │
大阪電気通信大学
エレクトロニクス
基礎研究所
共同研究装置
共同研究で利用する装置群です。
電気特性・ホール効果測定装置

測定試料表面の四隅に電極を形成し、試料表面に垂直に磁場をかけながら、対角線上に電流を流し、もう一方の対角線上の電極間に発生する電圧(ホ-ル電圧)を測定する。このことにより、試料中の移動可能な荷電粒子の密度が見積もれる。一方、van der Pauw法により、抵抗率も見積もれる。
温度可変型走査トンネル顕微鏡(VT-STM)

本装置は、ナノ構造・超薄膜形成過程を原子レベルで観察するための装置である。このため超高真空走査トンネル顕微鏡(STM)をメインとした構成になっている。本装置のSTMは観察中の温度を変化させることができる温度可変型である。
近接場光学顕微鏡システム

光の回折限界を超えた、数10~100nmの空間分解能で非接触測定が可能である。光学測定と試料表面の凹凸像取得を同時に行える。発光強度分布、反射測定、発光スペクトルの測定などが可能となっている。
超高真空マルチチャンバ・プラズマ実験装置

本装置は薄膜作製ならびにエッチングなどのプラズマプロセスに広く利用するために導入され、試料導入搬送室を介して3つのプラズマ生成室に基板(6インチウエハーサイズ)を真空搬送でき、それぞれのプラズマ生成室にてプロセス実験を行うことができる。
共同利用装置
共同利用装置として全学に公開している装置です。講習を受講すれば、院生、卒研生でも利用することができます。
X線光電子分光装置(ESCA)

軟X線照射によって放出した光電子の結合エネルギーを測定する方法で、物質の表面層(1~10nm)の組成元素やその結合状態、表面分子の構造、例えば、官能基の種類や量等を知ることができる。また、価電子帯スペクトルを測定したり、イオンエッチングにより組成元素及び化学状態の深さ方向の変化を知ることができる。
試料水平型X線回折装置(XRD)

X線の回折を用いて化合物の同定や物質の構造解析が行えるとともに、相・変態等の情報を得ることができる。無機、有機、金属、非金属、化学、高分子などの分野を問わず多方面で利用可能な基本的構造解析装置である。
粉末薄膜試料測定用X線回折装置(XRD)

2022年に導入された最新のXRD装置。全自動にて粉末測定、単結晶薄膜測定、ロッキングカーブ測定、X線の単色化が可能。
粉末回折データベースと検索

Powder Diffraction File(PDF)はICDD(International Centre for Diffraction Data)のJCPDS(Joint Committee on Powder Diffraction Standards)が編集・刊行した粉末X線回折データの最も充実したデータベースです。これを用いて、X線回折で測定した結果について、既知物質や未知物質の同定などができます。
原子間力顕微鏡(AFM)

試料表面に非常に小さなテコ(カンチレバー)を近づけて、試料表面とカンチレバーとの間に働く力(原子間力)を検出することによって、表面形状を観察する装置です。金属や半導体をはじめとして、セラミックス、有機物、高分子、生体試料等もコーティングなどの前処理をせずに大気中で観察が可能で、数百万倍という高倍率の試料表面の凹凸像が得られます。
レーザ顕微鏡

カラー「超深度」観察が可能で、観察倍率は50~16000倍である。カラー「超深度」画像では、モノクロ写真では判別することができない金属の腐食部分や、液晶の輝度欠陥などを即時に判断できる。また、あらゆる表面の「かたち」を3次元解析することも可能となっている。
顕微鏡デジタルカメラ

顕微鏡(金属顕微鏡および実体顕微鏡に取り付け可能)で観察した画像をスマートメディアに記録します。
フーリエ変換赤外分光(FTIR)

分子はそれぞれ固有の振動をしている。その分子に波長を変化させた赤外線(Infrared: IR)を連続的に照射していくと、主として分子固有の振動エネルギーに対応した赤外線が吸収され、分子の構造に応じた特有のスペクトルが得られる。この赤外吸収スペクトルから分子の構造などが解析できる。FTIRは、干渉計によって光源からの連続光の一部に光路を与えて、得られる干渉波(インターフェログラム)をフーリエ変換(Fourier transformation)して成分波のスペクトルを得る。
金コート専用イオンスパッタリング装置

絶縁性試料の帯電防止のために、金コートを行うイオンスパッタリング専用装置である。Arガス中のプラズマ放電で行なうものではなく、残留空気中のプラズマ放電で行なうものである。
高純水製造装置

水道水に水圧を加えてRO膜を通し、無機物97%有機物を99%除去し、その後連続式イオン交換モジュールEDIで更に高純度にして高純水を60Lタンクに蓄え、常時殺菌UVランプを照射し雑菌の繁殖を抑えている。
低真空SEM(含 ドライSDDエクストラ検出器)

低真空機能を内蔵し、導電処理できない試料や生物、医学、バイオ関連などの含水試料でもそのまま観察できる。高真空モードに切り替えて、高分解能撮影も可能である。元素分析を行うエネルギー分散形X線分析装置を内蔵している。
触針式表面計測プロファイラー

典型的には1mm以上の距離を1nmの高さ精度で、対象物の表面形状を数分で計測できる。面内方向の計測分解能は低い(数μm)が、数μm範囲での平均高さを再現性良く、短時間で測定できる点が、原子間力顕微鏡との違いである。
UV・可視光分光光度計

可視・紫外線領域の光を試料に照射し、その吸収強度から試料の同定、定量分析、電子状態の解析を行うことができる。
ナノ粒子物性解析装置


本装置は溶液中の粒子径を評価できる動的光散乱測定、分子量や慣性半径を評価できる静的光散乱測定、さらにナノ粒子のゼータ電位測定を行うことができる
高感度示差走査熱量計

電子スピン共鳴測定装置(ESR)

電子スピン共鳴を測定することで、不対電子をもつ物質の検出、同定、定量ができる。
その他の機器
電子天秤、超音波洗浄機、ホットコンプレート、電気溶接機