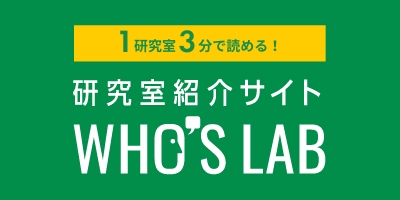MERI Activity Report (2023 Vol.24)
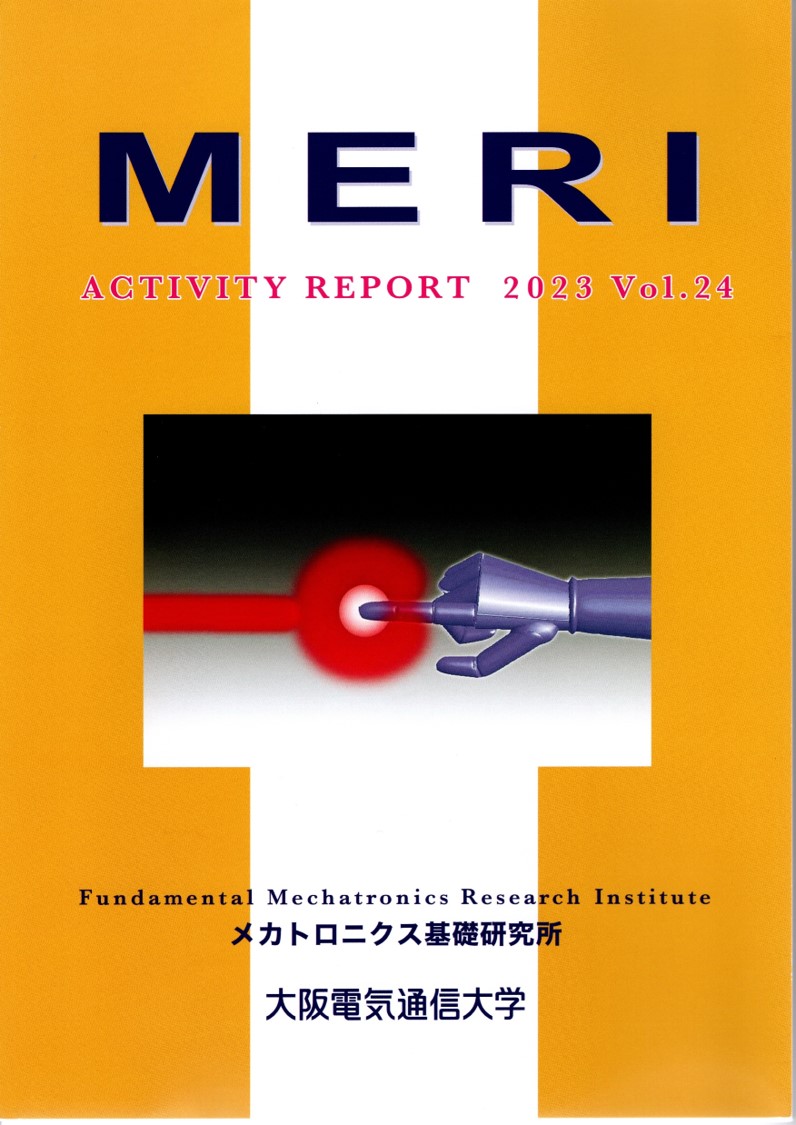
1.巻頭言(全文掲載)
メカトロニクスは本来の意味であるmechanismとelectronicsの融合という意味を超えて、制御(control)、情報(information)、計算機(computer)などの新しい技術分野を取り込みながら発展を続けています。これにより、製造業、航空宇宙、医療、自動車産業、防衛産業など、さまざまな応用分野を包含する総合的な技術体系へと進化しました。特に、昨今注目される「持続可能な社会(Sustainable society)」の実現に不可欠な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)達成には、複数の技術領域を統合(system integration)するメカトロニクスが重要な役割を果たすことは間違いありません。
話は変わりますが、近年の生成AIの進展には目を見張るものがあります。これほどのスピードで普及するとは予想もしていませんでした。調べてみますと、この技術は自然言語処理を基盤とし、マルコフ過程の確率モデルやニューラルネットワークが使用されているとのことです。これらの要素技術は30年以上昔、筆者が大学院生時代に学んだ内容です。添田・中溝・大松先生の信号処理の教科書と格闘したり、D. E. Rumelhartの有名なBack propagationに関する論文(1986年の出版なので当時は出たてのホヤホヤでした)を読んで「こんな上手いこと考える頭が良い人がこの世にはいるんだなあ」などと感心したことを思い出します。今思うともっと深く突っ込んで勉強しておけば・・と思います。しかし、当時はこれらの技術が生成AIを支えるまでになるとは思いもよりませんでした。なぜなら当時の計算機能力では、その理論を思い通りに実装するには不十分だったからです。ところがこの問題は、計算機技術の飛躍的な発展により解決されました。抽象化され積み上げられた理論に技術が追いつくことで実世界に革新的な発展をもたらす、まさにイノベーションの瞬間を目撃した気がします。
振り返って、ここから我々が学ぶべきことは基礎研究を継続して行うことの重要性です。工学では応用研究が重視されがちですが、基礎研究を軽視せず、現象に真摯に向き合い、規模を追わずに研究を進めることは、学術界に身を置く研究者の使命です。基礎研究を継続していくことが、長い目でみて人類社会の未来に貢献することを我々は常に心に留めるべきなのだと強く感じます。
さて、本学メカトロニクス基礎研究所は5部門の研究体制で研究・教育活動を行っております。その成果は、論文誌を含む各種著作物の発刊や学術講演会学会での発表などにより公表され、研究活動の活性化と学生の教育にも役立てています。2023年度の研究成果を見ると、共同研究の件数は45件、学外での発表件数は89件(国際会議、国内会議)に達し、研究員の皆さんの高い研究意欲が感じられます。
本冊子はこのような2023 年度の研究活動の内容をまとめたものです。読者の皆さまに興味を持って読んで頂けましたら幸甚です。
メカトロニクス基礎研究所 所長 入部 正継
(なおこの巻頭言の推敲はChat GPT 4o で行いました)
2.組織説明(以下、目次のみ)
3.共同研究報告
4.共同利用報告
5.講演会
6.研究報告
- はり理論から求めた影響係数を用いた曲げ荷重推定(井岡誠司)
- エンジン部品の最適設計に関する研究(新関雅俊)
- 超大容量スクロール圧縮機の性能評価(阿南景子)
- デジタル医療・看護・介護における人体やその臓器の計測や造形に関する研究(登尾啓史)
- HOT患者支援のための酸素ボンベ搬送用移動体ロボットに関する研究
~ MR流体クラッチを利用したバックドライバビリティの改善 ~(入部正継、遠藤 玄、小熊哲也) - 技術内容を可視化する教材用マニピュレータシステム(入部正継、友松竜太郎、鄭 聖熹、吉田浩治、衣笠哲也)
- 受動的動歩行の原理を応用した脚歩行機械の設計論に関する研究
~ 異なる力学系間の接続を利用した機械システム設計 ~(入部正継、福田海渡、大須賀公一、衣笠哲也) - ラズベリー果実の最適な自動収穫ロボティクス研究~ 生育管理モジュールのバックエンドシステム開発
~(入部正継、永澤一輝、堤 稜太、徳田献一、齊藤安貴子) - 天体観測のための補償光学の研究
補償光学装置の制御性能向上:大ストローク可変形鏡の自動調整機能(入部正継、大谷拓也、山本広大、木野 勝、栗田光樹夫) - 屋内外の難関バリアでの走行が可能な電動車いすRPwheel24-pt1の開発(鄭 聖熹 、小川勝史、杉本良太)
- かご型電車架線鉄柱の内部塗装用遠隔操作型マニピュレーターの開発(鄭 聖熹、高 言峰、小川勝史、上善恒雄)
- ドライマウス・ドライアイ診断支援手法に関する基礎研究(新川拓也、藤川智彦、橘 克典、西 恵理)
- ソフトコンピューティング技術によるシステムの知能化に関する研究(渡邊俊彦、徳山幸治)
- 3リンク倒立振子系のロバスト安定化
~ 変動領域を含む凸包の端点の個数に関する考察 ~(伊藤義道、渡邊俊彦) - 公開鍵暗号の安全性の検討と攻撃手法の有効性評価(境 隆一、村上恭通)
- 工場廃水の浄化およびダム湖の曝気循環に関する研究(中田亮生、水谷 満、高岡大造、岩松裕二、山岸真孝)
- BIMにおける環境影響評価手法に関する研究(添田晴生、辻 里実、飯島憲一)
- 室内空気環境に及ぼすパーティションの影響の調査検討(光石暁彦、中田亮生)