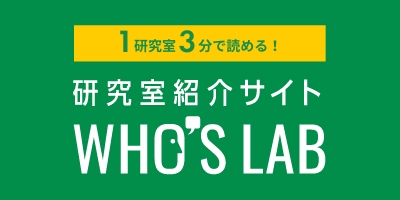MERI Activity Report (2021 Vol.22)

1.巻頭言(全文掲載)
本現在、メカトロニクスは本来の意味であるmechanismとelectronicsの融合という意味から発展を続け、制御(control)、情報(information)、計算機(computer)などの新しい技術分野を取り込んだ形へと発展を続けており、その応用を含めた総合的な技術体系として、製造業、航空宇宙、医療、自動車産業、防衛産業、などの応用先に至るまで幅広く包含する技術領域へと発展を続けています。近年話題になる「持続可能な社会(Sustainable society)」を実現するための持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)を可能にするのは、複数の技術領域の統合(system integration)を可能にするメカトロニクスであるのは間違いありません。
そのような学術領域であるメカトロニクスに対して、本学では前身であるメカトロニクス基礎研究施設の設立以来20年に渡りメカトロニクス基礎研究所にて、機械工学基礎/計測制御・ロボティクス/バイオエンジニアリング/電気・電子・情報/エネルギー・環境工学の5部門の研究体制で研究・教育活動を行っております。現在進められている共同研究のテーマでは、普遍的な内容である基礎研究から社会実装を視野に入れた応用研究まで多岐に渡っており、そのテーマ数は特定共同研究を含めて40件に上ります。
例えば機械工学基礎部門では、応用力学、流体力学、材料工学等の基礎研究や圧縮機に関する応用研究が行われています。計測制御・ロボティクス部門とバイオエンジニアリング部門関連では、ロボティクス・メカトロニクス技術を応用した医療支援の各種社会実装を意識した研究が広く行われており、変わったところでは天文学との学際的な研究なども行われています。さらに、電気・電子・情報部門での要素技術研究や、エネルギー・環境工学部門の基礎研究から社会実装を意識した応用研究など、メカトロニクス基礎研究所では非常に幅広い学術領域での研究活動が行われています。2020年以降のCovid-19の大流行による感染対策により、大学を取りまく研究環境が著しく悪化する中(※)で研究を継続している研究員と大学院生の積極的な研究活動の様子がうかがえます。
これらの研究成果は論文誌を含む各種著作物の発刊や学術講演会学会での発表などにより公表されています。また、学外の著名な研究者らによる講演会を開催するなど、研究の活性化と学生の教育にも役立てています。
本冊子はこのような研究活動の2021年度の内容をまとめたものです。読者の皆さまに興味を持って読んで頂けましたら幸甚です。
メカトロニクス基礎研究所 所長 入部 正継
2.組織説明(以下、目次のみ)
3.共同研究報告
4.共同利用報告
5.研究報告
- エンジン部品の最適設計に関する研究 (新関 雅俊)
- ナノ流体の数値熱流動解析のためのOpenFOAM用ソルバーの開発とその利用 (山本 剛宏、小柴 孝、辻中 優哉、大西 琢也)
- 壁面のごく近傍にある管の流体関連振動 (阿南 景子、中田 亮生)
- モデルベース開発における圧縮機要素のモデル化に関する実験的研究(阿南 景子、奥 達也、辻 琢磨)
- CGモデルを利用した先端的な手術支援システムに関する研究(大西 克彦、登尾 啓史)
- スマート農業用センサネットワーク構築に関する研究(小川 勝史、田中 和紀、二瓶 悠介、鄭 聖熹)
- 身体動作を利用したロボット操作インタフェースに関する研究(疋田 真一、伊藤 義道)
- ヒト運動時の二関節筋の筋活動と機構的効果の関係(藤川 智彦、万野 真伸、市谷 浩一郎、新川 拓也、小出 卓哉)
- 高感度集音デバイスを用いたネックバンド型呼吸モニタリング(松村 雅史、滝本 将大、水口 龍太)
- 徒手によるStrain ratio計測の検者内・検者間再現性(田中 則子、山田 大智、小柳 磨毅)
- 暑熱順化にともなう血管機能の変化(太田 暁美、岡﨑 和伸)
- 人体における体液動態と健康モニタリング(橘 克典、新川 拓也、藤川 智彦、片岡 明俊)
- 坑井を用いた地中物体の計測法に関する研究(海老原 聡、松本 将之)
- 3リンク倒立振子系の安定化制御(伊藤 義道、渡邊 俊彦)
- ダム湖等における深層の嫌気化要因の解明と対策に関する研究(中田 亮生、高阪 英樹、木屋 俊治、南 晧介、岩松 裕二、南出 拓)
- 最適環境創出技術に関する研究(高岡大造)
- 小規模ビール製造のための金属濾材による濾過プロセス(田中 孝徳、高岡 大造)