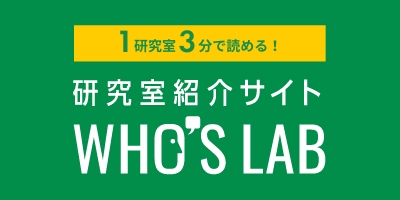2025.07.16
空間デザイン専攻1年生の授業で漆工芸家 北村繁氏の講演会を開催しました
7月4日(金)、建築・デザイン学科 空間デザイン専攻1年生を対象に「デザイン概論」の授業の一環として、漆工芸家 北村繁氏による特別講演会を開催しました。
北村氏は、大阪芸術大学芸術学部工芸学科金属工芸コースを卒業後、人間国宝・北村昭斎のもとで漆工品の修理および制作に従事。正倉院宝物をはじめとする国内外の漆工文化財の修復に携わる一方、公益社団法人日本工芸会に所属し、漆工芸の制作活動も精力的に行っています。現在は、日本工芸会正会員、文化財保存修復学会正会員、伝統技術伝承者協会理事、漆工史学会会員としてもご活躍されています。
講演では『漆工芸のいま・むかし ~螺鈿を中心に~』をテーマに、漆の基礎知識から文化財の保存・修復、創作活動まで、幅広い視点からお話しいただきました。
まず、漆とは何かについて、素材や採取方法、加工技法などの解説が行われました。漆は、ウルシ科の落葉高木から採取される天然樹脂で、堅牢性、耐久性、防水性、抗菌性に優れ、古来より器物や武具、建築装飾などに用いられてきました。特に、一本の漆の木から10〜15年かけて育てたうえで、わずか200gしか採れない希少性や、漆掻き職人の技術により支えられていることが紹介され、学生たちは真剣な表情で耳を傾けていました。
さらに、蒔絵(まきえ)、彫漆(ちょうしつ)、平文(ひょうもん)、螺鈿(らでん)といった装飾技法が紹介され、講演の中心となった「螺鈿」については、正倉院宝物《螺鈿紫檀五絃琵琶》を例に、歴史的背景や技法の魅力が詳しく語られました。また、江戸から明治にかけて、漆工芸が海外に輸出され、西洋の文化や価値観と交わりながら美術工芸として発展してきた歴史についても紹介されました。
講演の後半では、「文化財としての漆工芸を守る」という視点から、日常使いの漆器と文化財の保存修復の違いについて解説され、有形文化財や無形文化財、重要文化財、国宝など、体系図や文化財保存制度についても学ぶ機会となりました。
なかでも印象的であったのは、北村氏が携わった《螺鈿紫檀五絃琵琶》の模造制作で、調査や材料収集に7年、実制作に8年、あわせて15年という長い歳月をかけて取り組み、模造制作において忠実な再現の難しさと、真摯に向き合う姿勢の重さが伝わってきました。
講演終了後には、北村氏が手がけた漆工芸品が披露され、学生たちは実際に手に取って、その滑らかな質感や美しさを体感しました。
参加した学生からは「もともと文芸品や民芸品に興味があったので、このような貴重なお話を聞くことができ、とても勉強になりました。初めて漆器に触れ、その滑らかな感触に驚きました」「正倉院宝物などの歴史的な工芸品を通じて、漆工芸や歴史について知ることができ、興味が一層深まりました。昔のものを残す技術は本当に素晴らしいと感じました。これから建築を学ぶうえでも役立つと思います」と話してくれました。
学生たちにとって、日本の伝統工芸や文化財について理解を深める貴重な時間となりました。







.JPG)