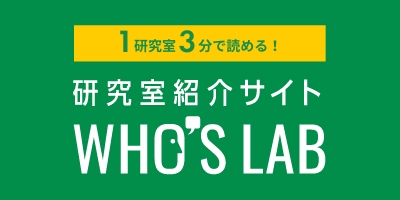2025.09.04
松居准教授が第24回日本VR医学会学術大会で招待講演と共同研究成果を発表
8月30日(土)、大阪大学吹田キャンパス銀杏会館(大阪府吹田市)で開催された「第24回日本VR医学会学術大会」で、総合情報学部情報学科 松居和寛准教授が招待講演および主導する共同研究の成果を発表しました。
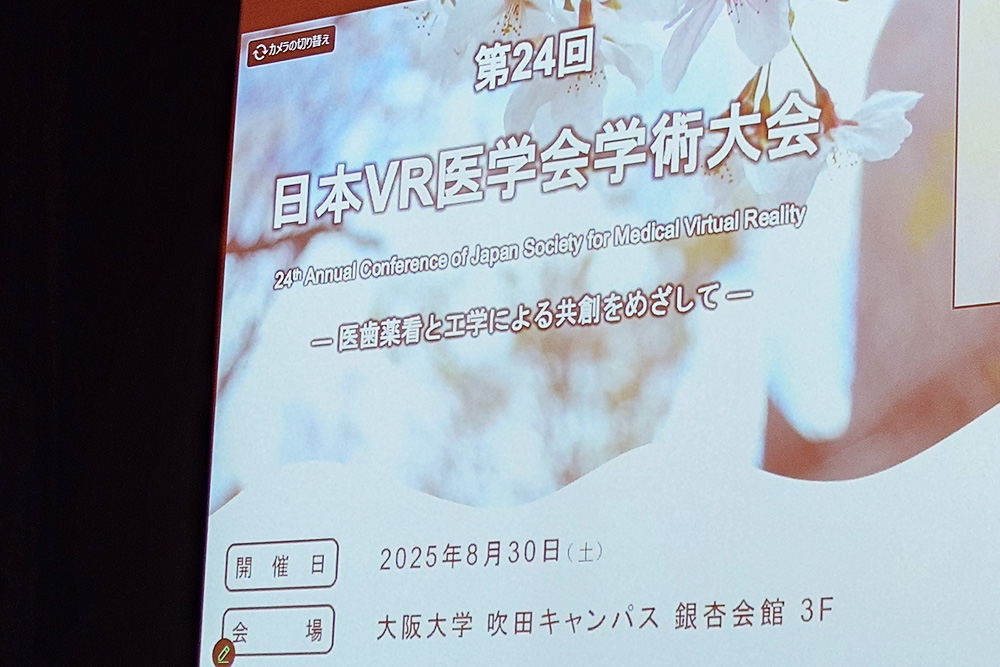
(1).jpg)
本大会は、医療の高度化とデジタル技術の発展に伴い、医工連携・融合の歴史を重ねてきました。バーチャルリアリティ(VR)の医学応用に関わる研究者や医療従事者、開発者、そして医療・看護・福祉の現場でVRの可能性に期待する人々が一堂に会し、分野の壁を乗り越え共に学ぶ学術交流の場として発展しています。また、VR医学の将来を担う学生たちの学びの場として新たな役割も担っています。
今回の大会テーマは「医歯薬看と工学による共創をめざして」です。
本大会の参加者同士が専門性と研究スタイルの同異をお互いに楽しみ、VR医学の新たな分野融合の気づきと多職種連携の輪を広げる「場」になる大会づくりをめざしました。
研究発表の内容は以下のとおりです。
■招待講演(ポスター発表)
テーマ:「一人医工情報学連携から医工産連携自律ロボット開発まで」
松居和寛(大阪電気通信大学 准教授)、西川敦(大阪大学 教授)
概要:本研究では、プロトタイピングから医工産連携の具体的事例まで幅広く提示した。理学療法士であり博士(工学)を取得した発表者が、自身の医学的知見から着想した医学的ニーズを基に、工学・情報学技術を用いたデバイス開発とプロトタイピングを行う「一人医工情報学連携」アプローチを紹介した。さらに、医学分野、工学分野、産業界の連携により、自律医療ロボットの開発を目指すプロジェクト事例を紹介し、医工産連携による研究推進の可能性について議論した。
■共同研究成果発表
テーマ:「筋電図駆動アバター適応後の運動パフォーマンスの検討」
児島凌馬(大阪大学 大学院生)、松居和寛(責任著者 大阪電気通信大学 准教授)、岡田耕太郎(大阪大学 大学院生)、藤井琉羽(大阪大学 大学院生)、厚海慶太(広島市立大学 助教)、森佳樹(大阪大学 助教)、平井宏明(大阪大学 准教授)、西川敦(大阪大学 教授)
概要:本研究では、筋電図で駆動する一人称アバター(Physio-Avatar EB)の体験が、体験者の運動パフォーマンスに与える影響を検討した。参加者は、実際の身体よりも動かしにくいと感じるアバターを操作した後、運動課題に取り組んだ。その結果、アバター体験後に運動パフォーマンスが向上する傾向が示され、運動能力向上や学習支援へのアバター活用の可能性が示唆された。
テーマ:「Virtual Self-touchを用いた足部伸長アバター身体化によるヒト歩行動作への介入可能性検討」
藤井琉羽(大阪大学 大学院生)、松居和寛(責任著者 大阪電気通信大学 准教授)、岡田耕太郎(大阪大学 大学院生)、児島凌馬(大阪大学 大学院生)、厚海慶太(広島市立大学 助教)、森佳樹(大阪大学 助教)、平井宏明(大阪大学 准教授)、西川敦(大阪大学 教授)
概要:本研究では、自身と異なる身体サイズのアバターを触覚刺激とともに体験するVirtual self-Touchを用いて、体験後の運動変容を検討した。足部が伸長したと知覚した場合、仮想的な障害物をまたぐ際の足部クリアランスが増加することを統計的に確認した。
第24回VR医学会学術大会
https://www.jsmvr.org/jsmvr2025
研究室紹介サイトWHO’S LAB(松居和寛准教授)
https://www.osakac.ac.jp/whoslab/research/matsui_k/
リハビリテーション医工情報学研究室
https://www.osakac.ac.jp/labs/rehalab/index.html
.jpg)

.jpg)