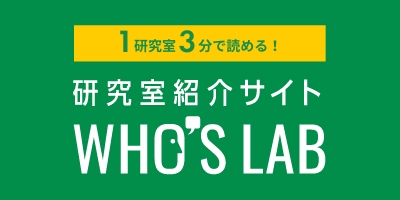建築・デザイン学部
建築・デザイン学科
(建築専攻)

建築・デザイン学科(建築専攻)
の記事一覧
2025.02.06
寝屋川市立中央小学校に廃材を使った「座れて 本が収納できる椅子」を寄贈
建築・デザイン学科 建築専攻 北澤誠男准教授が担当している「インテリア計画」では、2019年度から地域貢献・地域連携の一環として、本学...
2025.01.29
2024年度 建築学科4年生の卒業研究・卒業設計審査会を開催しました
1月21日(火)、22日(水)の2日間、多目的製図室(アトリエ)で4年生の卒業研究・卒業設計審査会を行いました。学生たちは、4年間の大...

2025.01.20
建築環境工学演習でパッシブハウス模型の設計製作・実験・プレゼンを実施
建築学科※3年生の後期授業「建築環境工学演習」では、「パッシブハウスを考える」というテーマで、一班3、4人でのグループワークの授業を行...

2024.12.17
まちづくり研究会が壁面ユニットを製作し京都府宮津市の町家に納品しました
まちづくり研究会の建築・デザイン学科建築専攻1年生のメンバーが、佐々木研究室の学外まちづくり活動の一環で、杉無垢材で壁面ユニット(格子...
2024.11.05
4年生の2回目の卒業研究・卒業設計 中間試問会を行いました
10月31日(木)、OECUイノベーションスクエア(A号館)3階の建築学科研究室で、工学部建築学科4年生の2回目の卒業研究・卒業設計 ...
2024.10.25
3年生「プレゼミナール」の授業で企業による講演会実施
10月7日(月)建築学科※3年生「プレゼミナール」の授業で、就職対策の一環として企業の方をお招きして「企業目線からの就職アドバイス」の...
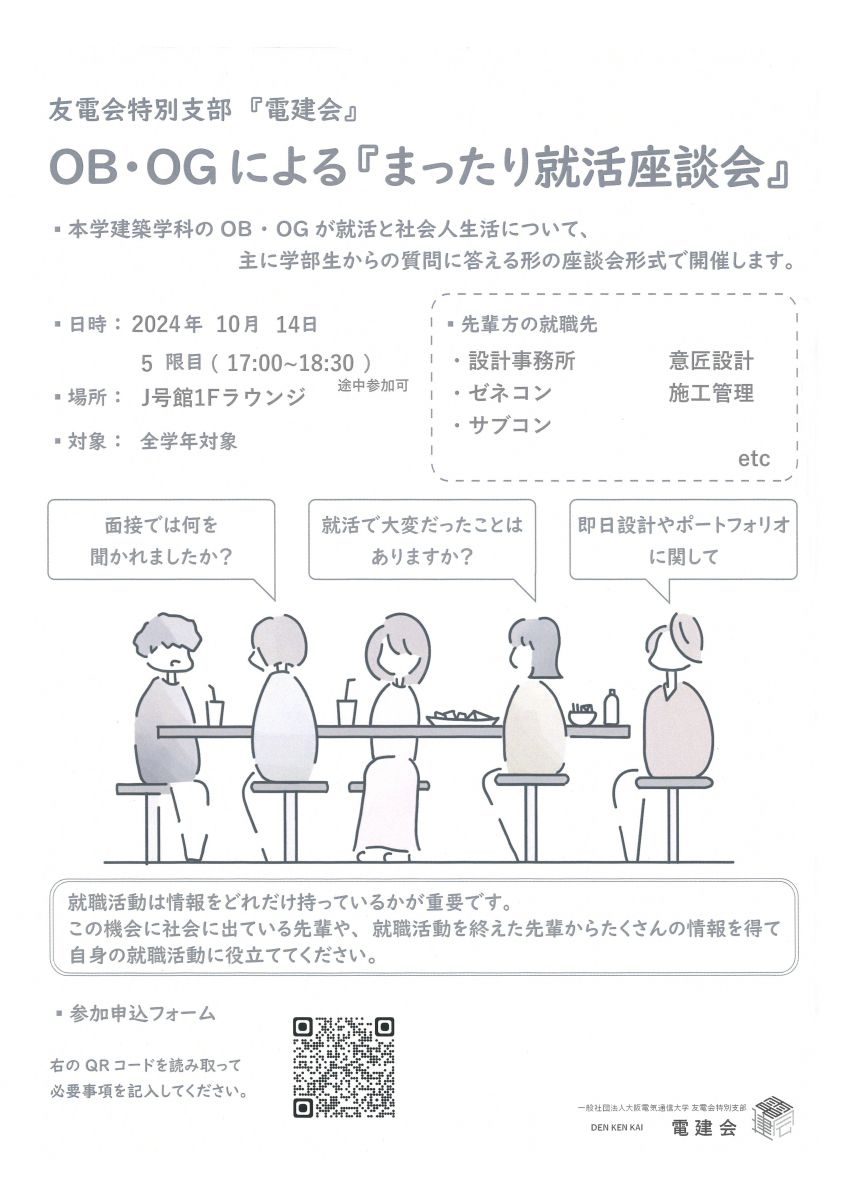
2024.10.22
電建会がOB・OGによる就活座談会を開催しました
10月14日(月)、エデュケーションセンター(J号館)1階ラウンジで、友電会特別支部「電建会」が建築学科※の学生を対象に、OB・OG、...
2024.09.20
令和6年度能登半島地震の災害ボランティア活動報告
9月10日(火)から9月13日(金)までの4日間、令和6年能登半島地震の被災地へ赴き、建築学科学生3人、工学研究科建築学コースの大学院...
2024.08.26
「町家デザインコンペ2023」最優秀賞学生インタビュー
昨年度に開催された「町家デザインコンペ2023」高校生の部で最優秀賞を受賞した鶴橋 千聖さん。現在は本学の建築・デザイン学科 建築専攻...
.jpeg)
2024.08.07
祇園祭山鉾巡行で学生らが曳き手として参加しました
祇園祭山鉾巡行で、佐々木研究室の学生5名が2022年に196年振りに復帰した【鷹山】の曳き手として参加しました。佐々木研究室では三条の...
2024.07.30
4年生の卒業研究・卒業設計 中間試問会を行いました
7月23日(火)、OECUイノベーションスクエア(A号館)3階の建築学科研究室で、工学部建築学科4年生の卒業研究・卒業設計 中間試問会...
2024.07.12
1年生「プロジェクト活動スキル入門」の授業で学外研修実施
建築・デザイン学部 建築・デザイン学科 建築専攻の1年生が「プロジェクト活動スキル入門」の授業の一環として、6月24日(月)、7月1日...
2024.07.09
ラボ委員が中心となり学生ラボの運営について意見交換を行っています
2022年に竣工したOECUイノベーションスクエア(A号館)の2階~3階では、日々学生らが研究活動を行っております。竣工から2年ほどが...

2024.07.04
2年生「キャリア概論」の授業で八木邸見学が行われました
6月27日(木)、建築学科※2年生対象「キャリア概論」の授業で、寝屋川市香里園にある八木邸の見学を行いました。この八木邸を設計したのは...
2024.07.04
鹿島建設株式会社による学内セミナー実施
6月27日(木)、工学部建築学科※3年生を対象に鹿島建設株式会社による学内セミナーが行われました。今回は、日本の大手総合建設会社である...
2024.06.21
3年生対象「キャリア設計」の授業で本学OB・OGによる業界職種研究会開催
6月12日(水)、工学部建築学科3年生を対象に「キャリア設計」の授業の一環で、本学OB・OGをお招きし就活座談会が行われました。この授...
2024.06.11
建築学科2年生の授業で本学OGと大学院生による講演が行われました
6月6日(木)、建築学科2年生のキャリア概論の授業で、本学OGと大学院生による講演が行われました。はじめに講演を行った本学大学院生の土...

2024.06.06
建築学科2年生の授業で株式会社竹中工務店による講演が行われました
5月30日(木)、建築学科2年生のキャリア概論の授業で、株式会社竹中工務店の加藤実悠氏(大阪本店設計部)による講演が行われました。加藤...
2024.05.27
3年生対象の「キャリア設計」の授業で業界職種研究会開催
5月22日(水)、工学部建築学科3年生を対象に「キャリア設計」の授業の一環で、企業、自治体をお招きして、建築職に関する特別講義が行われ...

2024.05.21
建築専攻の新入生が学外教育研修を行いました
5月11日(土)、建築・デザイン学部建築専攻の新入生が学外教育研修を行いました。本研修は、歴史的及び現代的な建造物の見学とスケッチを通...